雨の京都・祇園界隈を散策 八坂神社・知恩院 - 格安フェリーの旅 ― ― 2023-11-10
いつも使う、- 格安フェリーの旅 ―で、近江八幡、安土城を訪ねる計画をしてフェリーを申し込みました。 ところが、11月10日 行動する日のみが雨、天気予報を何度も確認したが、9時より16時は雨マーク!
で、予定変更して 雨の京都 白川、祇園界隈を散策にしました。
で、予定変更して 雨の京都 白川、祇園界隈を散策にしました。
八坂神社
「祇園さん」と親しまれる、全国八坂神社の総本社
八坂神社が「祇園さん」と呼ばれるのは、神仏習合時代の旧名「祇園社(ぎおんしゃ)」「祇園感神院(ぎおんかんしんいん)」の名残り。明治元(1868)年、神仏分離政策により、現在の「八坂神社」に改称されました。
八坂神社が「祇園さん」と呼ばれるのは、神仏習合時代の旧名「祇園社(ぎおんしゃ)」「祇園感神院(ぎおんかんしんいん)」の名残り。明治元(1868)年、神仏分離政策により、現在の「八坂神社」に改称されました。
四条通りの東端、花街側に位置する朱塗りの「西楼門」
「西楼門」は現存する境内最古の建造物で、応仁の乱(1467年~)で消失後、約30年後に再建されたものという歴史があります。
西楼門の大きさは桁行(幅)が7.9メートルで高さが9.1メートル
「西楼門」は現存する境内最古の建造物で、応仁の乱(1467年~)で消失後、約30年後に再建されたものという歴史があります。
西楼門の大きさは桁行(幅)が7.9メートルで高さが9.1メートル
西楼門。その両脇には、寺院の表門で見かける仁王像ではなく、随身(ずいしん・平安時代の貴族の護衛役)の木像2体が置かれています。
手水舎
太田社 重要文化財
西楼門をくぐって直ぐに鎮座する狛犬・獅子像
獅子像の台座には、水しぶきを上げ躍動する崇高な青龍の姿が描かれています。
北向蛭子社(きたむきえびすしゃ)
八坂神社石鳥居(重要文化財)
本殿の正面入口の鳥居。正保3年(1646年)に建立、寛文2年(1662年)の地震で倒壊、寛文 6年(1666年)に補修再建されたもの
本殿の正面入口の鳥居。正保3年(1646年)に建立、寛文2年(1662年)の地震で倒壊、寛文 6年(1666年)に補修再建されたもの
八坂神社南楼門 ・・・本殿の正面に向かった南門が八坂神社の正門です。
舞殿(ぶでん) 国の重要文化財
八坂神社舞殿は入母屋造(いりもやづくり)の銅板葺(どうばんぶき)です。八坂神社舞殿は一直線に並ぶ本殿・南楼門と同じ高さで、三位一体(さんみいったい)を表しているとも言われています。
八坂神社舞殿は入母屋造(いりもやづくり)の銅板葺(どうばんぶき)です。八坂神社舞殿は一直線に並ぶ本殿・南楼門と同じ高さで、三位一体(さんみいったい)を表しているとも言われています。
本殿は2020年、国宝に指定されました。八坂神社独自の稀少な建築様式と注目されています。
本殿と拝殿(礼堂)が大屋根ひとつで覆われ、1つの建物として建築される様式は平安時代に成立。南北朝時代には現在の本殿とほぼ同じ構造だったそうです。
本殿と拝殿(礼堂)が大屋根ひとつで覆われ、1つの建物として建築される様式は平安時代に成立。南北朝時代には現在の本殿とほぼ同じ構造だったそうです。
日吉社 重要文化財 八坂神社の鬼門に鎮座されているのが日吉社です。
八坂神社の境内末社の日吉社(ひよししゃ)には大山咋神(おおやまくいのかみ)と大物主神(おおものぬしのかみ)が祀られています。
八坂神社の境内末社の日吉社(ひよししゃ)には大山咋神(おおやまくいのかみ)と大物主神(おおものぬしのかみ)が祀られています。
本殿の北側の参道
東北門より円山公園へ
円山公園から知恩院の南門を抜けて、知恩院 三門へ向かいます。
浄土宗の総本山で知られる「知恩院(ちおんいん)」。国宝の三門・御影堂に加え、数多くの重要文化財が存在しています。
知恩院 三門(国宝)
高さ24m・横幅50m・屋根瓦約7万枚と、日本最大級の規模を誇る木造門。1621年、徳川2代将軍秀忠公の命で建立されました。
高さ24m・横幅50m・屋根瓦約7万枚と、日本最大級の規模を誇る木造門。1621年、徳川2代将軍秀忠公の命で建立されました。
御影堂(国宝)
浄土宗の開祖「法然上人」の御影(みえい)を祀ることから、「御影堂(みえいどう)」と呼ばれています。
御影堂は、1639年に徳川家光によって再建され、間口45m・奥行き35m・幅3mの外縁をめぐらした巨大な伽藍となっています。
浄土宗の開祖「法然上人」の御影(みえい)を祀ることから、「御影堂(みえいどう)」と呼ばれています。
御影堂は、1639年に徳川家光によって再建され、間口45m・奥行き35m・幅3mの外縁をめぐらした巨大な伽藍となっています。
大鐘楼へ向かいます。
大鐘楼 (重要文化財)
鐘楼は延宝6年(1678)、知恩院第38世玄誉万無上人のときに造営されたものです。
釣鐘は高さ3.3メートル、直径2.8メートル、重さ約70トン。寛永13年(1636)、知恩院第32世雄誉霊巌上人の鋳造です。知恩院の釣鐘は、京都方広寺、奈良東大寺と並ぶ大鐘として知られています。
鐘楼は延宝6年(1678)、知恩院第38世玄誉万無上人のときに造営されたものです。
釣鐘は高さ3.3メートル、直径2.8メートル、重さ約70トン。寛永13年(1636)、知恩院第32世雄誉霊巌上人の鋳造です。知恩院の釣鐘は、京都方広寺、奈良東大寺と並ぶ大鐘として知られています。
御影堂
なだらかな「女坂」です。参拝者のほとんどがこの坂を帰り道として利用します。
東大路通へ向かう知恩院道
再び、白川筋へ向かいます。






















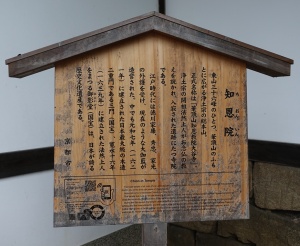


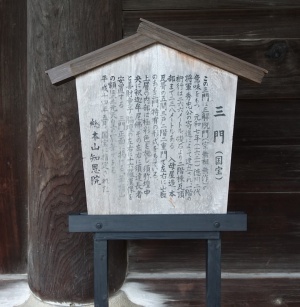










コメントをどうぞ
※メールアドレスとURLの入力は必須ではありません。 入力されたメールアドレスは記事に反映されず、ブログの管理者のみが参照できます。
※なお、送られたコメントはブログの管理者が確認するまで公開されません。