麻生大浦荘 紅葉特別公開 - 福岡県飯塚市立岩1060 ― 2022-11-24
( 写真をクリックすると拡大されます。)
特別公開が始まりました、ドライブがてら 麻生邸を訪れました。
麻生大浦荘は「筑豊御三家」のひとつに数えられた麻生家の住宅として建築され、現在は麻生グループのサロンとして利用されています。ふだんは邸宅も庭園も非公開となっていますが、この期間だけ美しい庭園の紅葉を楽しむことができます。
通常は非公開なので、当然案内板や看板などはありません。
表通りに運営の方が案内に立っておられました。 感謝!
手指消毒、検温で対策が・・・
玄関前の寄せ木、麻生系住宅の特徴らしいです。
山桃、金木犀、銀木製との説明を受けました。
もともと個人住宅として建てられたため、建築資料がなく建築年次は不明だそうです。建物に残された銘などから大正13年(1924)には完成したのではと思われるそうです。
玄関
玄関間
畳廊下
二階下から仏間にむかって
二階下から畳廊下、庭園側を望む
畳廊下に、警報機。下は昔のサイレンでしょうか?
応接間
書院造りを基調とした洋広間は、明治期大邸宅のスタイルだそうです。
次間、座敷
座敷より庭園を望む
内玄関、玄関
【 庭園 】
「 ヒールの靴はスリッパに履き替えてください」との案内が・・・
紅葉シーズンに一週間無料で公開されています。
関係者の皆様の対応にも感謝です。ありがとうございます。
PS: 回転寿司一太郎で食事をして、旧伊藤伝右衛門邸に向かいましたが
11/24、25はお休みでした。 で、大分八幡宮に寄って帰りました。
大分八幡宮 - 福岡県飯塚市大分1272 ― 2022-11-24
( 写真をクリックすると拡大されます。)
大分八幡宮(飯塚市)
大分八幡宮(だいぶはちまんぐう)は 古代に神功皇后が三韓征伐から帰国して 当地で引率していた軍士を解隊し それぞれの故郷に返した時 その大分(オオワカレ)から大分(ダイブ)と称されるようになったと伝わります 筑前国一之宮の「筥崎宮(福岡市)」の元宮とされています
大分八幡宮(だいぶはちまんぐう)は 古代に神功皇后が三韓征伐から帰国して 当地で引率していた軍士を解隊し それぞれの故郷に返した時 その大分(オオワカレ)から大分(ダイブ)と称されるようになったと伝わります 筑前国一之宮の「筥崎宮(福岡市)」の元宮とされています
御祭神 : 応神天皇(八幡大神)、 神功皇后、 玉依姫命
創祀 : 神亀3年(726)
創祀 : 神亀3年(726)
一の鳥居のそば(道路側)の、この石は何でしょうか?
一の鳥居
愛らしいポーズの狛犬さん
二の鳥居 昭和3年(1928)に建立された
三の鳥居 元禄3年(1690)に建立された
手水舎 大きな一枚岩でできているようです
総門 「随神門」
宝永4年(1707)、村中の人々が願主となって建立された総門は、切妻造り、銅板葺、朱塗の八脚門。年代のみでなく、通常は寺院にある仁王像が安置されているところも、神仏分離以前の形態をそのまま遺しているもので貴重です。仁王像も、宝永4年(1707)の造像とみられ、こちらも郡中の人々により寄進されたものです。仁王像は筑穂町指定有形文化財です。
宝永4年(1707)、村中の人々が願主となって建立された総門は、切妻造り、銅板葺、朱塗の八脚門。年代のみでなく、通常は寺院にある仁王像が安置されているところも、神仏分離以前の形態をそのまま遺しているもので貴重です。仁王像も、宝永4年(1707)の造像とみられ、こちらも郡中の人々により寄進されたものです。仁王像は筑穂町指定有形文化財です。
神社に仁王門は珍しいです。佐賀神埼の九年庵入り口にも、仁比山神社の仁王門があったのを思い出しました。
仁王像の裏にある随神様と狛犬
社殿
平成7年(1995)に建立された現在の社殿は、祭典や参拝の場となる千鳥破風唐破風付の拝殿、幣帛を奉るための幣殿、そして本殿からなっています。本殿は中央に応神天皇(八幡大神)、左に神功皇后、右に玉依姫命を祀っています。かつては、天正5年(1577)に建てられた本殿、慶安3年(1650)に建てられた拝殿がありましたが、老朽化のため、平成7年(1995)に、遠近多くの人々の力を集めて、新たに現在の社殿が建てられました。
平成7年(1995)に建立された現在の社殿は、祭典や参拝の場となる千鳥破風唐破風付の拝殿、幣帛を奉るための幣殿、そして本殿からなっています。本殿は中央に応神天皇(八幡大神)、左に神功皇后、右に玉依姫命を祀っています。かつては、天正5年(1577)に建てられた本殿、慶安3年(1650)に建てられた拝殿がありましたが、老朽化のため、平成7年(1995)に、遠近多くの人々の力を集めて、新たに現在の社殿が建てられました。
社務所
悠久社
江戸時代のものである総数48点74枚の絵馬が大切に保管されてあります。
江戸時代のものである総数48点74枚の絵馬が大切に保管されてあります。
天満宮
大神宮
社殿向かって右手の鳥居から石階段を上って丘の中腹に鎮座するのが天照大神を祀る大神宮です。宝永2年(1705)に社人の井上内蔵が建立したもので、11月6日19時の例祭日には、祭典につづき、嘉穂神楽が奉納されています。
社殿向かって右手の鳥居から石階段を上って丘の中腹に鎮座するのが天照大神を祀る大神宮です。宝永2年(1705)に社人の井上内蔵が建立したもので、11月6日19時の例祭日には、祭典につづき、嘉穂神楽が奉納されています。
生目神社
平家の侍大将であった平景清は、壇ノ浦の合戦に敗れて日向に流されました。源氏の世を悲しんだ景清は、自ら両目をくり抜き盲目となり生涯を閉じたと伝えられています。その死後、景清の徳を称えた住民が日向国の生目神社に合祀したとされています。平景清の徳を称え、御神詠の「かげ清く照らす生目の水かがみ、末の世までもくもらざりけり」を三回唱えると眼病平癒の御神徳を得られるとされています。
平家の侍大将であった平景清は、壇ノ浦の合戦に敗れて日向に流されました。源氏の世を悲しんだ景清は、自ら両目をくり抜き盲目となり生涯を閉じたと伝えられています。その死後、景清の徳を称えた住民が日向国の生目神社に合祀したとされています。平景清の徳を称え、御神詠の「かげ清く照らす生目の水かがみ、末の世までもくもらざりけり」を三回唱えると眼病平癒の御神徳を得られるとされています。
御神木
神功皇后は、三韓征伐から戻るときに三本の樟を持ち帰り、香椎宮・宇美八幡宮・大分八幡宮の三社にそれぞれ植えたと伝えられています。福岡県天然記念物指定を受けている御神木の樟は、その子孫とされています。大陸系の樟で、推定樹齢が約700~800年、胴周り径が約9mです。
神功皇后は、三韓征伐から戻るときに三本の樟を持ち帰り、香椎宮・宇美八幡宮・大分八幡宮の三社にそれぞれ植えたと伝えられています。福岡県天然記念物指定を受けている御神木の樟は、その子孫とされています。大陸系の樟で、推定樹齢が約700~800年、胴周り径が約9mです。
道路側にも大きな楠木がそびえています。
弁財天と「殺生禁断」の石柱がある放生池
市杵島神社
放生池の畔には、宗像三女神の市杵島姫神を祀る市杵島神社が鎮座しています。市杵島姫神は仏教の弁才天と習合したことから、弁才天(弁財天・弁天)とも呼ばれています。
放生池の畔には、宗像三女神の市杵島姫神を祀る市杵島神社が鎮座しています。市杵島姫神は仏教の弁才天と習合したことから、弁才天(弁財天・弁天)とも呼ばれています。
恵比寿社
一の鳥居の向かって左手に鎮座するのは事代主を祀る恵比寿社です。
一の鳥居の向かって左手に鎮座するのは事代主を祀る恵比寿社です。
大分八幡宮 福岡県飯塚市大分1272
「大分(だいぶ)八幡宮」は奈良時代、神亀3(726)年の創建とされています。祭神は八幡神((応神天皇(おうじんてんのう))・神功皇后(じんぐうこうごう)・玉依姫命(たまよりひめのみこと)です。
平安時代の延長元(923)年に、八幡神が大分宮(だいぶぐう)から博多湾岸の筥崎(はこざき)へ遷座するという出来事が起こりました。大分八幡宮が筥崎宮(福岡市東区)の元宮と言われるのはこのためです。その後も大分八幡宮は、宇佐八幡宮(大分県宇佐市、現在の宇佐神宮)の「九州五所別宮」第一に位置づけられるなど、由緒正しい名社として存続しています。
境内には、神功皇后が三韓の役から帰国の際に持ち帰った3本の樟のうちの1本の子孫であると言われる大樟があります。推定樹齢は約350年、幹回りは約9mで福岡県指定天然記念物です。
また、応神天皇の産湯に使ったとされる井戸や、仁王像が安置される神仏習合時代の様式を今に伝える総門(楼門)、弁財天と「殺生禁断」の石柱がある放生池なども見どころです。
創建当時の社殿は現在地より後方の丘陵上にありましたが、戦国時代に戦乱のため消失。天正5(1577)年に秋月種実(あきづきたねざね)が現在地に再建しました。現在の社殿は拝殿、本殿とも平成7(1995)年に改築されたものです。 (福岡県「ご来福」しよう HPより)
「大分(だいぶ)八幡宮」は奈良時代、神亀3(726)年の創建とされています。祭神は八幡神((応神天皇(おうじんてんのう))・神功皇后(じんぐうこうごう)・玉依姫命(たまよりひめのみこと)です。
平安時代の延長元(923)年に、八幡神が大分宮(だいぶぐう)から博多湾岸の筥崎(はこざき)へ遷座するという出来事が起こりました。大分八幡宮が筥崎宮(福岡市東区)の元宮と言われるのはこのためです。その後も大分八幡宮は、宇佐八幡宮(大分県宇佐市、現在の宇佐神宮)の「九州五所別宮」第一に位置づけられるなど、由緒正しい名社として存続しています。
境内には、神功皇后が三韓の役から帰国の際に持ち帰った3本の樟のうちの1本の子孫であると言われる大樟があります。推定樹齢は約350年、幹回りは約9mで福岡県指定天然記念物です。
また、応神天皇の産湯に使ったとされる井戸や、仁王像が安置される神仏習合時代の様式を今に伝える総門(楼門)、弁財天と「殺生禁断」の石柱がある放生池なども見どころです。
創建当時の社殿は現在地より後方の丘陵上にありましたが、戦国時代に戦乱のため消失。天正5(1577)年に秋月種実(あきづきたねざね)が現在地に再建しました。現在の社殿は拝殿、本殿とも平成7(1995)年に改築されたものです。 (福岡県「ご来福」しよう HPより)
大分八幡宮の大樟 - 福岡県飯塚市大分1272 ― 2022-11-24
巨樹・巨木――その定義とは?
1988年に環境庁が初めて全国規模での巨樹・巨木林調査を行った際、
「地上から130cmの位置で幹周(幹の円周)が300cm以上の樹木を対象とする」と定め、
現在ではこれが一般的な定義となっています。
何千年、何百年も生き続けている巨樹・巨木
福岡県・佐賀県に、全国巨木第10位内にランクされている巨木が5つもあります。
福岡から日帰りで行ける範囲で訪問しています。
1988年に環境庁が初めて全国規模での巨樹・巨木林調査を行った際、
「地上から130cmの位置で幹周(幹の円周)が300cm以上の樹木を対象とする」と定め、
現在ではこれが一般的な定義となっています。
何千年、何百年も生き続けている巨樹・巨木
福岡県・佐賀県に、全国巨木第10位内にランクされている巨木が5つもあります。
福岡から日帰りで行ける範囲で訪問しています。
大分八幡宮の大樟 - 福岡県飯塚市大分
大分八幡宮 御神木
神功皇后は、三韓征伐から戻るときに三本の樟を持ち帰り、香椎宮・宇美八幡宮・大分八幡宮の三社にそれぞれ植えたと伝えられています。福岡県天然記念物指定を受けている御神木の樟は、その子孫とされています。大陸系の樟で、推定樹齢が約700~800年、胴周り径が約9mです。 福岡県指定天然記念物(1956年7月28日指定)
神功皇后は、三韓征伐から戻るときに三本の樟を持ち帰り、香椎宮・宇美八幡宮・大分八幡宮の三社にそれぞれ植えたと伝えられています。福岡県天然記念物指定を受けている御神木の樟は、その子孫とされています。大陸系の樟で、推定樹齢が約700~800年、胴周り径が約9mです。 福岡県指定天然記念物(1956年7月28日指定)
大分八幡宮(飯塚市)
大分八幡宮(だいぶはちまんぐう)は 古代に神功皇后が三韓征伐から帰国して 当地で引率していた軍士を解隊し それぞれの故郷に返した時 その大分(オオワカレ)から大分(ダイブ)と称されるようになったと伝わります 筑前国一之宮の「筥崎宮(福岡市)」の元宮とされています
大分八幡宮(だいぶはちまんぐう)は 古代に神功皇后が三韓征伐から帰国して 当地で引率していた軍士を解隊し それぞれの故郷に返した時 その大分(オオワカレ)から大分(ダイブ)と称されるようになったと伝わります 筑前国一之宮の「筥崎宮(福岡市)」の元宮とされています
一の鳥居の並び、道路側にも大きな樟が・・



























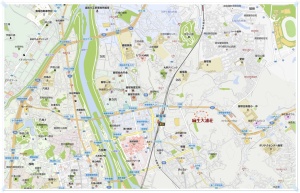


































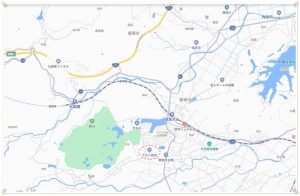




最近のコメント